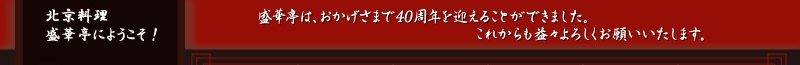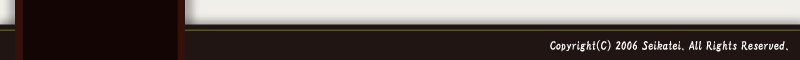| 戻る |
 |
NO.16 2003/12/04
「中国野菜について」 |
 |
 |
最近ではさまざまな中国野菜が市場で手軽に手に入るようになりました。
十数年前ではチンゲン菜ですら珍しかったものです。。。
今やすっかり日本の食卓に溶け込んだものから、まだまだ珍しい野菜まで、いくつか御紹介いたします。
終戦当時、鴨川のほとりに住んでいた中国人の人たちが、自分達の食用のために川岸に中国野菜を栽培していたそうです。
じっくり目を凝らして探すと、いまだにその頃の名残りがあるとか、ないとか。。 |
 |
| (参考文献 世界文化社発行 『人気のチャイニーズ』より) |
 |
| 「中国野菜の種類」 |
 |
 |
チンゲンサイ
日本でも特に有名。盛華亭でももっとも良く使われます。
ほとんどあくが出ないのでさっとゆがいて料理のそえにも使います。
もともと白菜の一種で、小株ほど柔らかくて風味豊か。
茎まで青いので、中国読みで青い茎の野菜(チンゲンサイ)といわれます。 |
 |
タアツァイ
炒めもの、煮物によく使われる。チンゲンサイの一種で、日本でも年中売られています。
しかし旬は冬で、霜にあたってはじめて旨味が出ます。タアツァイの「タア」はへばりつくという意味で、葉がまるで葉牡丹を潰したような状態で育ちます。 |
 |
バイゲンツァイ
チンゲンサイと同じ白菜の一種で、チンゲンサイの茎を白くした様。
それゆえバイ(白)ゲンツァイと言われます。日本では広東白菜とも言われるように、広東周辺が主産地です。 |
 |
クウシンサイ
茎の中が空洞になっているので空心(クウシン)菜といいます。
さつまいも属の夏野菜で、柔らかい若葉と茎を食します。
主に炒め物に使用します。
青臭さがある反面、カルシウムやカロチンといった栄養豊富な野菜です。 |
 |
ジャオバイ
日本では「まこもだけ」と呼ばれています。
しかし見た目がタケノコに似ているのでこう呼ばれてますが、本当はイネ科の水生植物。
炒め物に使われ、色が白く、淡白であっさりとした味です。 |
 |
ウオスゥン
「ちしゃとう」といえば御存じの方も多いはず。
レタスの一種で、主に葉を食べます。非常に太い茎も中心部の柔らかいところは食べられます。茎はタケノコのように千切りにしてから下処理してから使います。
葉は炒めもの等に使われます。 |
 |
まだまだ中国でしか手に入らないものも沢山あります。
しかしこれらの中国野菜は日本の市場にも多く出回るようになりました。
最近では和洋中といった料理もジャンルを超えて様々な試みがなされております。
今まで手に入らなかった食材が簡単に使えるようになったのもそれに拍車を加えているように思えます。 |
 |
| ▲このページのTOPへ |
| 戻る |
 |